原田正憲という書家がいた。私の叔父である。
二十代で日展に入選したが既成の権威を否定して、1964年、江口草玄・井上有一氏
らの墨人会に参加した。その十年後、これも退会。以来、その身をどこにも置かず属さず、
在野で書き続けた。自分のしていることは果たして「書」であるのか、どこを目指せばいい
のか、問うべき仲間もういない。自らをそんな境地に追い込んだのだ。厳しさと寂寥、そして
清々しさを道づれの、孤 であった。
原田正憲は正しく言えば夫の叔父なので、血のつながりはない。けれど実の姪のよう
に可愛がってもらった。叔父の一家と野山に遊び、土ひねりを指南してもらい、猪鍋を振る
舞われた。
叔父からの手紙や葉書が届くと、私たち夫婦はいつも四苦ハ苦した。判読不能な文
字が一行のうち何カ所も出てくるからだ。夫は幼い頃からその字に接しているにもかか
わらず解読を早々にあきさらめ、「これ、ちゃんと届くのが凄いなあ」と、宛名を判読しおせ
た郵便屋さんに感心した。
叔父の書がいかなるものであったのかをここで表現するのは難しいのだけれど、原田
正憲という人そのものであったことは確かである。
生まれてきたこの世をじっくりと味わい、誰かが無駄だと切り捨てたものを拾い上げ、
見つめる。それが面白いと感ずると、目尻を下げて微笑んだ。法事の場でふいに滑稽な
ことを言い出す俗気も私には好もしく映って、今もそれを思い出すたび胸の裡が明るくなる。
家族に一度も声を荒げたことのなかった叔父には、ぎざりと鋭角に尖った部分もあった。
小器用に書いたものに溜息を吐き、誰かの模倣に片眉を顰め、自分を飾った賢げな物言い
には無言で返した。そして理不尽だと思う事には真っ向から立ち向かった。そんな時、必ず
独りだった。
高校の書道教育の場では、手本を与えない主義を貫いた。誰かが用意したものに従う
な、若い命のままに生き生きと書けばこそ、いい字 なのだと説き、生徒らと共に墨にまみ
れた。
叔父の鉢が癌に蝕まれていることがわかったのは、四年前のこと。幾度もの手術を経
た後もあゆる抗癌剤に挑戦し、壮絶な副作用にもね音を上げなかった。
正直に申せば、私はその姿に微かな違和感を抱いていた。勝手に、一体禅師のごとく
捉えていからだ。世の中は起きて稼いで寝て食って 後は死ぬのを待つばかりなり・・・
なのに叔父は死に抗い続ける。その理由が、私にはどうしても掴めなかった。
後に叔母と話しをしていて、胸を衝かれた。叔父は妻をこの世に置き去りにすることが
忍びなかったのだ。自らを 孤 に追い込むことはしても、妻を独りにすることには断固とし
て抵抗した。実に叔父らしい生きようだったと、今は思う。
私が直木賃を受賞した時、叔父は痛み止めの絶え間ない服用で朧朧としていたにもかか
わらず、総身を輝かせんばかりに喜んでくれた。もはや自宅で最後を迎えんとする時期に入っ
ていたが、私は贈呈式と受賞パーティーヘの招待状を出した。招待状は叔父の棺に納めら
れた。
叔父は自らの作品集「孤 原田正憲の書」の刊行をも待たずに逝ってしまったけれど、
巻頭の文章にこんな一節がある。
筆を置いたその時、もっと書きたい、もっと書きたいと思いました。
こんなに書きたいと思ったことは、未だかつてありません。
『招待状』文藝春秋 月刊 6月号
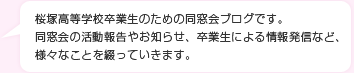
コメントする